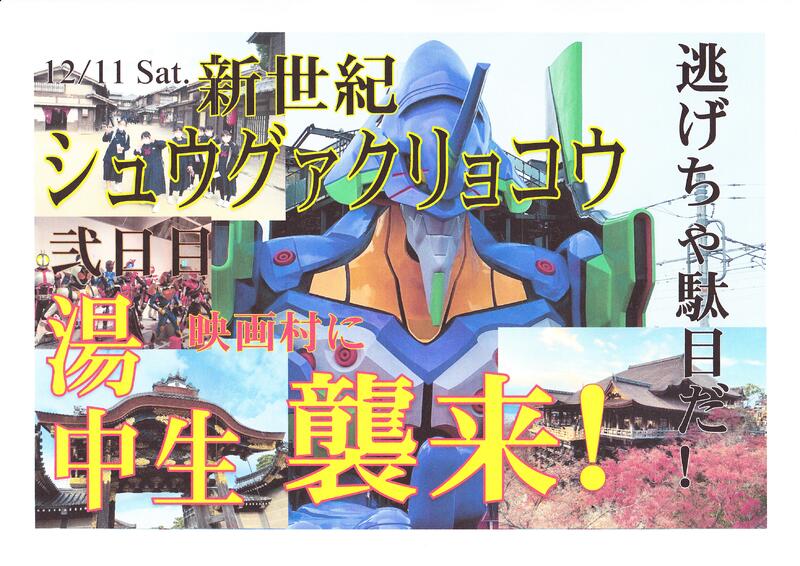亀城ヶ丘だより
【東映太秦映画村】031211
怖かった〜。みんなで慰めています。終わった後は絵馬の前で。良いことがありますように。草野先生、山口先生もチャレンジしました。(前田先生は医師に止められている、私は孫が生まれたばかりで命を失うわけにはいかない。という正当な理由で入りませんでした。怖いわけではありません。)
【湯中生参上!】031211
映画村に湯中生参上!大量のフィギュアを見て舞いあがっています。ケースの中に入りたいと言っていましたが、何のフィギュアでしょう?
水戸黄門のパネルの前でご飯を食べて、見学に向かいます。お化け屋敷が一番人気のようです。
【金閣!】031211
みんな楽しみにしていた鹿苑寺金閣に到着、背の高い竹垣抜けると突然現れる金閣の美しさに声がもれました。良く晴れていて、みんな素晴らしい写真が撮れました。写真コンテストをしたいですね。
【ウグイスはどこにいる?】031211

【バッチリです】031211
残さず食べて、あと片付けまでバッチリをパチリ。さて、どの席でしょう?
【修学旅行2日目】031211
修学旅行2日目の予定は以下の通りです。
8:45二条城
10:10鹿苑寺金閣
11:20太秦映画村
14:20三十三間堂
15:10音羽山清水寺
17:40なごみ宿「都和」着
【おはようございます】031211


【班長会議】031210
班長が集まり、1日目の反省をしています。このあと、しおりのまとめをして休みます。しっかり寝て明日に備えます。
【夕食】031210
夕食の時間。Jくんの感想発表の後、同じ方向を向いて黙食です。何杯もおかわりをして動けません。
【進撃の仁王像】031211
東大寺に到着するや否や鹿の歓迎を受けました。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 漆島未央
運用担当者 教諭 伊高久美子
☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。
R7 40週.pdf(2/16~2/20)
☆令和7年度の行事予定
2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)
2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト
3/4・5 公立高校後期選抜
3/6 3年生修了式
3/8 卒業証書授与式
3/9 振替休業日
3/24 1・2年生修了式(給食なし)
☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)
防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。
必要なデータをダウンロードしてご活用ください。
研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。
<防災教育関係リンク>
総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)