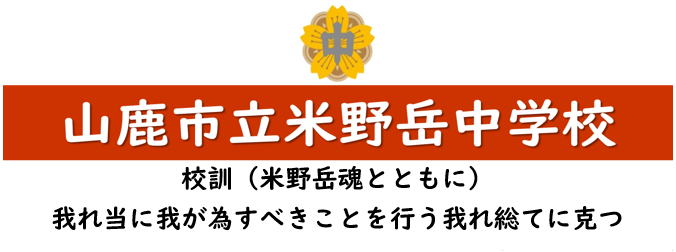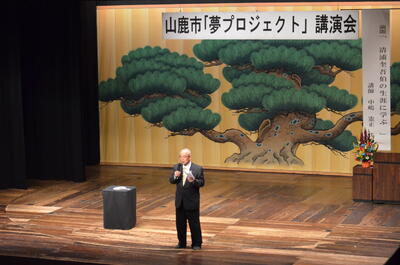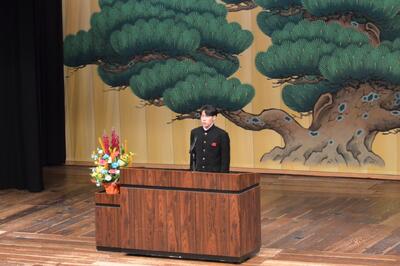令和7年度 校長室から
「夢プロジェクト」講演会
12月19日 2年生が山鹿市「夢プロジェクト」講演会に参加しました。
この講演会は、山鹿市が毎年開いている講演会で、山鹿市内の中学2年生が八千代座に一堂に会し、山鹿に縁のある方や各方面で活躍されている方のお話を聴き、子供たちに夢を膨らませてほしい願いから開かれています。
今回は前山鹿市長で清浦奎吾顕彰会会長の中嶋憲正様に「清浦奎吾伯に学ぶ」と題して、講演をしていただきました。
いにしえに倣うと、14歳は元服の年で、立志式を行うところもありますので、今回の夢プロジェクトが子供たちにとって、十五の春を前に、叶えたい夢をもつことや郷土に誇りをもつ切っ掛けになることを願っています。
ご講話の中で、中嶋様は、ご自身が大切にされている3つのことを話されました。
一つ目は、好きになることです。
「好きこそものの上手なれ」と、言うように、「自分を好きになること」そして、「下手な自分を、欠点を含めて好きになること」を大切にされているそうです。また、「好きになるためには一生懸命にすること。」「一生懸命にしていると、多くの人に支えられる。すると、感謝する気持ちも生まれ、幸せになる」とも話されました。
二つ目は、元メジャーリーガーのイチロー選手の言葉です。
「小さいことを重ねることが、どんでもないところへ行くただ一つの道なんだ。」に共感され、これを実践に活かしておられます。
三つ目は、人生の岐路に立ったら、必ず厳しい道を選ぶこです。
「安易な道ではなく、自分にとって厳しい道を選んで進むことで、道を切り拓くことができる」と、語られました。中嶋様のこれまでの実践や生き方に重なるようにでした。
この他に、清浦奎吾翁から学び、ご自身の生き方に生かされていることもお話になられました。
〇命の不思議さを感じ、選ばれた命を大切にすること。
〇咸宜園の咸宜が意味する「みんないい」のように、一人一人のよさである個性を大事にすること。
〇人としての人権を大切にすること。
〇四恩(「親の恩」「先輩の恩」「友(朋友・同僚)の恩」「時世の恩」)を忘れないこと。
これらを交えながら、2年生に受け継いでほしい思いを、バトンをつなぐように情熱的にお話しいただきました。
この夢プロジェクト講演会から、2年生は先人の教えや生き方からたくさんのことを学び得たようです。
講演会の最後には、本校生徒が閉会のあいさつを立派にすることもできました。2年生一人一人の学びと夢をもつチャンスをいただいたことに心から感謝します。
かぼちゃを頂戴しました
11月17日 三玉にあります立山農産の 立山 和宏 様(山鹿市教育委員)から、学校給食用に南瓜をいただきました。収穫後の保存状態が良い南瓜は色つやも良く、見るからに甘くて美味しそうです。大きさも揃っていますので、調理にも好都合のようです。
近々、この南瓜を使ったメニューが給食に出るそうです。どんなパンプキン料理になるのか楽しみです。
人権教育実践レポート研修会
12月10日 校内研修で人権教育実践レポートの書き方(綴り方)について学びました。研修会の講師には、もくせい学園職員で米野岳中学校に勤務されていた 松永 康一 様をお迎えして、レポートの内容やレポートを書くときに大切にすることを具体的な事例を交えながら、説明していただきました。
この夏、「部落差別をはじめあらゆる差別をなくす熊本県人権教育研究大会」で報告された松永先生のお話には説得力があり、貴重な学びの時間になりました。
今回、松永先生から人権教育実践レポートの書き方についてご講話をいただく機会を得られたことを大変ありがたく思いますし、ご協力いただきましたもくせい学園施設長様ほか関係するすべての皆様に心から感謝申し上げます。
ご講話の中で、松永先生は「差別をなくしていくために大切なことは、思いやりや同情ではなく、『人間を尊敬すること』である。これは、水平社宣言の核にもなっていて、自分の言葉で、『人間を尊敬するとは?』をいえるようになってほしい」と、お話になったことが大変心に残っています。また、私たちが人権教育実践レポートを書くことは、自分を語り、自分を誇ることであり、親子とつながり、なかまとつながる実践であることを改めて確かめることができました。
これからの教育や社会には、異なるものを排除するのではなく、多様性の包摂がいっそう求められます。それは、私たちが学校教育の基盤に据えてきた人権教育の取り組みをより大切に、丁寧に実践することにつながります。
私たちは、今後も部落差別をはじめすべての差別をなくす人権教育をしっかりと推進してまいります。
第2回小中合同PTAリサイクル活動
12月7日 第2回小中合同PTAリサイクル活動を、めのだけ小学校グラウンと駐車場で行いました。寒い朝でしたが、たくさんの中学生のボランティアや保護者の方々にご協力いただき、回収・運搬や分別作業をスムーズにしていただきました。皆様に協力に心から感謝いたします。
このリサイクル活動で、中学生はアルミ缶のリサイクル回収を担当しました。一度にたくさんのアルミ缶を届けていただくこともありましたが、子供たちは回収していただいたアルミ缶を自動車から下ろして、大きなフレコンバックへどんどん移し入れ、アルミ缶とその他のものとの分別もすばやくしていました。予定していた時間は2時間30分でしたが、あっという間に過ぎてしましました。
PTAの各役員の皆様、地域の皆様には早朝からご協力をいただき、誠にありがとうございました。今回のご協力いただきましたリサイクル活動の収益金は、小学校・中学校ともに子供たちの学校生活や学習に有効活用して参ります。今後もどうぞよろしくお願いします。
市学調・県学調にチャレンジ
12月5日 子供たちが熊本県学力・学習状況調査を受けました。今年度から、調査の方法が変わって、国語・数学・英語・調査用紙の全てをCBT方式で行うことになりました。
CBT(Computer Based Testing)とは、問題も解答用紙もコンピュータ画面上にあり、子供たちは、タブレットPCを操作しながら解答するテストです。
調査テストの時間、子供たちの机の上には、問題用紙も解答用紙もありません。鉛筆で書いて答えることもなく、子供たちはタブレットPC画面を見て、読んで答案を入力しながら進めます。紙媒体の調査テストに馴染んだものには、教室の風景がちょっと違ったものに感じました。
しかし、これから子供たちがCBT方式の調査問題を受けることは増えてきますので、子供たちには日本語のローマ字入力やキーボード入力に慣れさせる必要があるようです。
子供たちは、12月4日にも、山鹿市学力・学習状況調査を受けています。また、1年生は8日まで、2年生は9日まで調査テストが続きます。
テストは自分の力を知るよい機会ですし、教師にとっても学習指導の振り返りになるチャンスです。ですから、まずは精一杯、テストにチャレンジさせたいと思います。
九州中学校駅伝競走大会4位
11月29日 九州中学校駅伝競走大会が長崎県諫早市のトランスコスモススタジアム長崎で開催されました。大会には九州各県の代表男子18校が集まり、どの学校もこれまでの練習の集大成となるレースを展開しました。
米野岳中駅伝チームもスタートから上位に着け、抜きつ抜かれつのしながらも懸命に走り、襷を繋ぐレースをしました。九州の猛者が集まった大会を4位で終えた選手たちのしなやかでしたたかな走りは立派でした。スタジアムに米野岳魂を残すこともできたと思います。
大会を終え、駅伝チームの子供たちのこれまでの努力を心から労います。お疲れさまでした。
そして、大会出場に当たりご支援、ご協力いただきましたすべての皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
レース前に駅伝チームがそろって円陣を作り、目標を確認し合いました。ピーカンの清々しい朝です。
人権教育講演
11月28日 人権教育講演会を開きました。今回は、横手純子様と補助犬で盲導犬のちよちゃん、春木雄一朗様を講師にお迎えして、視覚に不自由さや障がいを持たれた方の思いや暮らしを知り、共に生きることへの願い聴くことができました。
横手さんと春木さんは、病気が原因で目が不自由になられた中途視覚障がい者の方々です。そのご自身の経験から、視覚障がい者の日常や困り感を生徒や他のたくさんの皆さんに知ってもらい、すべての人が包摂さる共生社会をつくることを願い、講演活動をされています。
その熱意は、行政を動かす力にもなっています。市議会議員の方々も、当事者のお話を聴き、障がいを持たれた方々の思いを、共生するまちづくりに活かそうと、今日の講演会に参加され、熱心に講話をお聴きになられました。
子供たちは、これから共生社会を築いていく一員として大切な役割を担います。その担い手とし、子供たち一人一人に求められるのが、豊かな人権感覚であり、差別問題に対する基本的な認識であると改めて思いました。
お話の中で、「誰かの当たり前は、他の誰かにとっては壁になっている。」とおっしゃったのには大変納得しました。そして、この壁を作っているのは私たちであることを改めて感じました。子供たちにとっても、このセンテンスは大変印象深いことばになったようです。
障がいをもった方々にとって、その事象はその人そのものであり、障がいがあることは問題ではなく、現象であるだけです。ですから、障がいを取り除くちょっとした手助けがありば、障がいはなくなるとおっしゃったのも大変心に残りました。
今回の人権教育講演会の内容を聴いて、子供たちには、障がいをもった方々の生きづらさに共感したり、差別問題に直面されていることに思いを馳せてほしいと思います。そして、障がいをもった方々に自分から関わりをもち続け、必要な合理的な配慮を考え、行動を起こす人になってほしいと思います。
今も起きている障がい者への差別問題も部落差別の問題も、すべての人権問題は、差別される側に問題があるのではなく、差別する側の問題であることを、いつも心に留め、すべての人々が安心して暮らすことができる共生社会をつくる一員に、子供たちがなっていくことを願っています。期待しています。
横手さんは、盲導犬のちよちゃんを貸与されてから、生活が変わったとお話になりました。
外に出て誰かと歩くことができる安心感は、いつも誰かの助けを受ける生活から、自立した生活に変わるきっかけとなり、自信になったそうです。そして、ちよちゃんと歩くことで、生活も行動も明るい方へ、明るい方へ、前へ、前へいけるようになり、人が集まる場所へ行ったり、運動をしたり、おしゃべりをしたりすることを心から喜んでおられます。
春木さんは、5年前に突如視力を失った体験から、私たちの生活がどれだけ視覚に頼っているのかをわかりやすく教えてくださいました。
今、私たちは暮らしの中で、さまざまな情報をいろいろなメディアから得ていますが、その情報の8割から9割は見ることによって得られる視覚による情報だそうです。それで、視覚が閉ざされるとどのくらい不自由さを感じるかを、子供たちに体験させ、ものの形をつかむことや伝えることの難しさを学ばせていただきました。
春木さんは、視覚障がいについてもっと周りの人々に知ってもらい、共に生きることを一緒に考えていきたい願いをもたれておられます。それで、体育館へ案内する子どもたちに、手引きして誘導することを頼まれていました。子供たちも、手引き誘導をしてみて分かったことや感じたことがあったようです。
山鹿市長を表敬訪問しました
11月25日 山鹿市役所に市長訪問に行きました。先日の熊本県中体連駅伝競走大会の報告と九州中学校駅伝競走大会出場のあいさつにをすることができました。
山鹿市長早田順一様と教育長堀田様から、県大会での頑張りをお褒めいただくとともに、九州大会での活躍を期待する激励のお言葉を頂戴しました。
音楽部が準グランプリ受賞
11月22日 熊本県立劇場で熊日学生音楽コンクールが開催されました。本校から音楽部が参加し、「朧月夜」と「おてもやん」の2曲の合唱を発表しました。そして、見事に準グランプリの日本製紙賞を受賞しました。おめでとうございます。
1月にはこの受賞者演奏会がありますので、これからもしばらく吹奏楽と合唱の両方に取り組んで行きます。応援をどうぞよろしくお願いします。
また、音楽部の生徒は11月2日の熊日学生音楽コンクールの独唱の部の予選にも出場しています。そして、3名の子供たちが、12月13日に熊本市男女共同参画センターはあもにいで開催されます本選に出場する予定です。こちらも応援をどうぞよろしくお願いします。
食育のサポートで頂戴した新米をいただきました
11月21日 今日の給食に、先日、元田様からいただいた新米「にこまる」が提供されました。
炊きたての白いご飯は、もちもちした触感で、かむほどに甘みが感じられて大変美味しゅうございました。
元田様のご厚意に感謝いたします。
(きょうの献立) ごはん(新米「にこまる」) 甘酒入り豚汁
さんまのかばやき ほうれんその白和え 牛乳
どのメニューも大変大変結構なお味でした。温かくて、ボリュームも愛情もいっぱいの調理をしていただいた給食室の先生方に大感謝です。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 森 晋一郎
運用担当者 教諭 渡邉 陽一
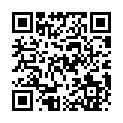
携帯・スマホにURLを送ります。
上記のQRコードをQRコードリーダー
で読み取って下さい。
令和7年度
生徒会年間目標
生徒会年間目標 「わらうめのには かちきたる」
日本教育工学協会(JAET)により、学校情報化優良校として再認定していただきました。認定期間は、2025/06/28 ~ 2028/03/31です。初回認定は2021年度。
山鹿市立米野岳中学校
〒861-0561
熊本県山鹿市鹿央町岩原1350番地
TEL 0968-36-3151
FAX 0968-36-3152
y-menodakejh@educet01.plala.or.jp
URL http://jh.higo.ed.jp/menodakejhs
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 1 | 3 | 4 1 | 5 2 | 6 2 | 7 |
8 | 9 1 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 |
15 | 16 1 | 17 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |