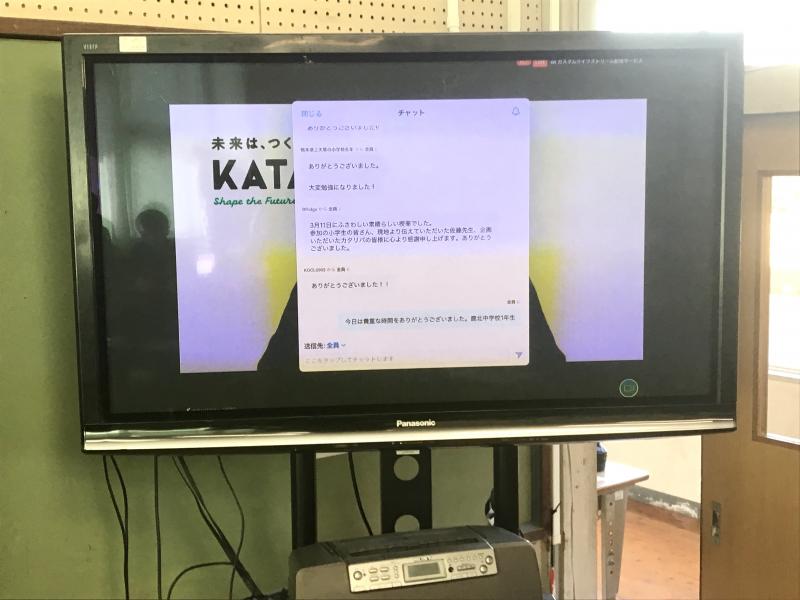【学校生活】3.11東日本大震災から今日で10年
3月11日(木)今日で東日本大震災から10年が経ちました。しかし、まだまだ復興の途上にあります。
1年生は、10時00分より、カタリバオンライン特別プログラム、旧大川小から全国の子どもたちへ届ける「防災と命の授業」 ~もしもはいつもの中に~に参加しました。
この授業には、全国から2000人以上の小中高生が参加しました。
授業を行うのは、大川小学校で当時12歳のお子さんを亡くされた、女川第一中学校元教諭・佐藤敏郎氏。
旧大川小では、東日本大震災で全校児童の7割に当たる74名の児童と10名の教職員が死亡・行方不明となりました。
多くの犠牲者がでたこの学校を建て壊すのか、残していくのか、地域全体での長い議論の末に震災遺構として未来へ残していくことが決定し、この春、防災・減災に関する学びの場として、新しいスタートを迎えようとしています。
「大川小学校はよく『あの大川小』と言われます。それは、悲惨な場所、悲しい場所という意味で。
しかし、大川小のフェンスには、未来を拓くと今も掲示されている。
みなさんは、『大川小をどんなところ』と聞かれたら、『未来を拓く場所』と答えてほしい。
地震発生は、14時46分。大川小の時計は、15時37分で止まっている。
この地震発生から津波が来るまで51分間ある。この51分で何があったのか。
近くには歩いて1分で登れる山がある。でも避難できなかった。
大津波警報がでていたが、校庭にとどまっていた。
そして、最後の1分で逃げた。
山に登れば助かった。しかし、橋の方向へ逃げて亡くなってしまった。
なぜ、逃げられなかったのか。
1分間 自分の心の中の思い、気持ちを書いてほしい。」
「なぜ、あの時逃げることができなかったのだろう?10分間話しあってください。」
津波がここまでは来ないと思っていた
大丈夫だと思っていた
学校は安全と思っていた。
パニックになってしまった
誰も想定していなかった
津波が発生することを予想していたのに、対応できなかった。
富士山噴火、南海トラフ、予想しているが、今日は大丈夫だろうとどこかで思っている。
自分たちは大丈夫だろうとどこかで思っている。
あの日大事だと思ったことは、今日も大事。
空気と同じ。みんな気づかない。なくなって始めて大切さがわかる。
命も一緒。
何事もない時に準備。
山に登るスイッチを入れる。スイッチをいれやすくしておく。
逃げる人の中に自分も入っていることを想定してほしい。
ここは学校だった。名前のシールが今も残っている。
道はつながっている。ここから未来を拓くことを考えてほしい。
「佐藤先生のお話を聞いて、大川小学校は、悲しい場所じゃない。未来を拓く場所だということが、あらためてわかりました。私が思う『未来を拓く』とは、東日本大震災などで学んだことを、日常に生かしていくことだと思います。」
「佐藤先生のお話を聞いて、『もしも』は『いつも』の中にある、と言われたのが心に残りました。それは、『もしも何かが起きたら』と言うけれど、その『もしも』は、いつものように過ごしている時に起こりうると思うからです。『もしも』は『いつも』の中にある、だから僕は自分の命を一番にし、大切なものを守っていきたいです。
「私は、佐藤先生の、『防災は助かるためにする。だから、避難訓練は、自分の家族や自分の命のことを考えてしてほしい。そうすれば、本気になってできる。』という言葉が心に残りました。
『もしもはいつもの中にある』と『危機的状況になってから気づいても遅い』、この2つの言葉を頭に入れて過ごしていきたいです。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 西浦 伸一
運用担当者 教諭
◆熊本県教育広報誌
ばとん・ぱす vol.79
◆熊本県人権情報誌
コッコロ通信 vol.59
山鹿市立 鹿北中学校
- Kahoku Junior high school -
住所:〒861-0601 熊本県山鹿市鹿北町四丁1464番地
Tel:0968-32-2019
Fax:0968-32-3797
E-mail:y-kahokujh@educet01.plala.or.jp
URL:https://jh.higo.ed.jp/kahokujh/